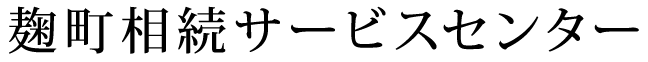死亡直後にやってはいけない6種類の相続手続き

大切な人を失った際は、気持ちの整理がつかない中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。
相続手続きの中には期限が定められているものもありますが、死亡直後に行うべきではない手続きもあるため注意が必要です。
本記事では、死亡直後に避けるべき6種類の相続手続きについて解説します。
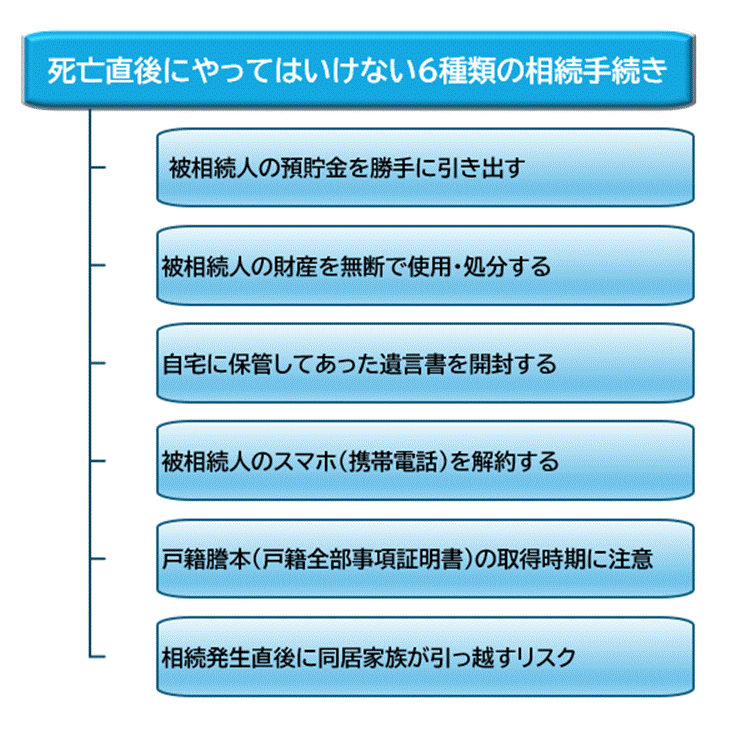
被相続人の預貯金を勝手に引き出す
金融機関に相続が発生したことを伝えると、被相続人(亡くなった人)の口座が凍結されます。口座凍結は、第三者が勝手に口座内のお金を引き出さないようにするための措置ですが、相続手続きが完了するまでの間、預貯金の管理が制限されます。
口座が凍結される前にお金を引き出す選択肢もありますが、相続後に勝手にキャッシュカードやインターネットバンキングを利用して引き出そうとすると、法的に問題となる可能性があるので注意が必要です。
また、口座内のお金も相続財産の一部ですので、本来相続人間で分ける財産を無断で使用したことが原因で、他の相続人との間でトラブルになることもあります。
そのため、相続が発生しましたら、金融機関に死亡を伝え、遺産分割協議が完了した後に相続手続きの流れに従って正式に払い戻しを受けるようにしましょう。
なお、遺産分割完了までの期間、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金を必要とする場合は、「相続預金の払戻し制度」を利用できます。
所定の手続きを行えば、家庭裁判所の判断を経ずに、同一の金融機関から最大150万円まで引き出すことが可能ですので、被相続人の預金から生活費を出していた場合は、相続預金の払戻し制度を活用してください。
被相続人の財産を無断で使用・処分する
遺産相続では、相続人同士が話し合って、財産ごとに引き継ぐ人を決定します。遺産分割が完了するまでは相続人全員が財産を引き継ぐ権利を持っているため、被相続人の財産を無断で使用したり、売却(譲渡)することは避けるべきです。
万が一、遺産分割協議で取得者が決まっていない財産を勝手に処分してしまうと、相続トラブルの原因となる可能性があるため気を付けなければなりません。
また、相続財産の分割を円滑に進めるためには、相続発生時点で被相続人が所有していた財産を正確に把握し、財産目録を作成することが重要です。
遺産分割協議完了後に新たな財産が判明した場合は、再度相続人間での話し合いが必要となるため、協議を行う前に相続財産を漏れなく把握しましょう。
自宅に保管してあった遺言書を開封する
遺言書には、相続財産を渡す相手が記されていることが多く、遺言内容によっては財産の分配が大きく変わる場合があります。被相続人が自宅に遺言書を残していた場合、相続人であっても遺言書を勝手に開封すると、法律に抵触する可能性があるので注意が必要です。
遺言書には種類があり、「自筆証書遺言」については家庭裁判所での検認手続きをしなければなりません。
検認前に遺言書を開封すると、法的効力が認められなくなる恐れがあるため、自宅で遺言書を見つけた際は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください。
被相続人のスマホ(携帯電話)を解約する
被相続人が使用していたスマホや携帯電話は、相続財産を把握するための重要なツールです。銀行や証券会社の認証情報や契約内容の確認など、相続手続きを円滑に進めるために必要なデータが含まれている可能性があるため、急いで解約すると相続財産の把握が困難になる場合があります。
契約書や郵便物などから財産の存在を確認できることもありますが、オンライン契約のサービスなどについては、インターネット上にしか情報が保管されていないこともあります。
スマホを解約してしまうと、財産を把握する手段が失われる可能性がありますので、被相続人名義のスマホに重要な情報が含まれていないか確認し、必要なデータをバックアップした上で契約解除を行いましょう。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取得時期に注意
相続開始日から10日以上経過した後に作成された戸籍謄本でなければ、相続手続きを進められない場合があるため注意が必要です。相続手続きで使用する戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、相続発生時点の被相続人および相続人の存在を証明する書類として用います。
しかし、死亡直後に取得した戸籍謄本は、戸籍整理が完了しておらず、最新情報が反映されていない可能性があります。
役所に死亡届を提出しても、戸籍の変更処理が完了するまでには時間がかかるため、数週間経過してから取得するのが望ましいでしょう。
相続発生直後に同居家族が引っ越すリスク
被相続人と同居していた家をすぐに離れると、被相続人に対する連絡や郵便物に対応することができなくなります。相続手続きの過程で、被相続人が残した契約書や銀行の通知などが必要になりますし、連絡の行き違いはトラブルの要因となるため、相続手続きが落ち着いてから住まいをどうするか検討してください。また、相続税の節税の観点で考えた場合、相続税の申告期限前に引っ越しをしてしまうと「小規模宅地等の特例」を適用できなくなる恐れがあります。
小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額する制度ですので、引っ越し時期には注意が必要です。
相続手続きがわからない場合は専門家に相談すること
相続手続きを相続人だけで進めると、手続きミスや申請漏れが生じる可能性があります。誤った対応をすると、相続人間でトラブルになるだけでなく、法的な問題が出てくることもあります。
たとえば、相続税の申告が遅れた場合、加算税や延滞税のペナルティが課されるリスクも生じるので注意が必要です。
相続に関する不安を解消するためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、手続きをスムーズに進められるだけでなく、誤った対応によるトラブルを未然に防ぐことができますので、大切な財産を適切に扱うためにも専門家の力を借りることを検討しましょう。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする