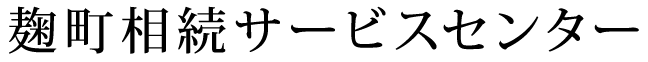相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットと税制改正のポイントを解説

「相続時精算課税制度」は、贈与税の特例であると同時に、相続税にも影響を及ぼす制度です。
制度を適切に活用すれば大幅な節税効果が期待できますが、単に適用するだけでは効果が得られない場合もあるため、注意が必要です。
本記事では、相続時精算課税制度の概要、メリット・デメリット、令和5年度の税制改正による主な変更点について解説します。
相続時精算課税制度の概要:仕組みと基本ルール
令和5年度の税制改正を前提とすると、相続時精算課税制度とは、原則として「60歳以上の父母または祖父母など」から、「18歳以上の子または孫など」に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
ただし、当該贈与が令和4年3月31日以前の場合は、「贈与を受ける子や孫は20歳以上」となります。
相続時精算課税制度を選択すると、最大2,500万円の特別控除に加えて、年間110万円の基礎控除を適用することができ、基礎控除額+特別控除額を超えた贈与財産については一律20%の贈与税がかかります。
基礎控除額の110万円は毎年適用できるのに対し、特別控除額は累積管理される控除枠なので、2,500万円から差し引いた残額を翌年に繰り越すことになります。
贈与財産の種類に制限はありません。
ただし、相続時精算課税制度を選択した特定贈与者(父母または祖父母など)から贈与を受けた財産の価額については、特定贈与者の相続発生時(死亡時)の相続財産の価額に持ち戻され(含められ)、相続税額の計算を行うこととなるため、制度選択時には慎重な検討が必要となります。
ここからは、より詳しい制度内容と、制度のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
令和5年度の税制改正における相続時精算課税制度の変更点
相続時精算課税制度は、令和5年度の税制改正で大幅に変更されました。
相続時精算課税制度の基礎控除額の創設
相続時精算課税制度における110万円の基礎控除額は、令和5年度税制改正により新たに創設された控除です。
この基礎控除額は、令和5年以前に相続時精算課税制度を適用していた場合でも、令和6年以降の贈与に対して適用可能です。
従来は、制度適用後に特定贈与者から贈与を受けた場合、翌年以降も贈与額の大小にかかわらず申告が必要でしたが、改正後は贈与額が110万円以内であれば申告は不要となります。
また、令和6年1月1日以後の贈与については、110万円の基礎控除額を差し引いた後の金額が、相続税の計算に加算される相続時精算課税適用財産となります。
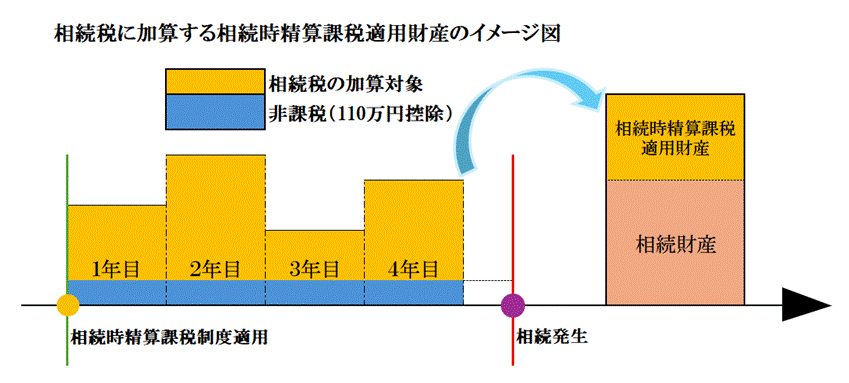
【計算例:3,000万円を贈与する場合の贈与税】
(1)1年でまとめて贈与する場合
3,000万円 - 110万円 = 2,890万円
2,890万円 - 2,500万円 = 390万円
390万円 × 20% = 78万円(贈与税額)
※相続税への加算対象金額【2,890万円】、贈与税額控除額【78万円】
(2)5年(毎年600万円)に分けて贈与する場合
600万円 - 110万円 = 490万円(1年分)
(490万円 × 5年) - 2,500万円 = 0円(贈与税額)
※相続税への加算対象金額【2,450万円】、贈与税額控除額【0円】
災害による被害を受けた贈与財産の相続税評価の特例の創設
令和6年1月1日以降の災害により、相続時精算課税制度を適用して取得した土地・建物が一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格に加算される評価額を減額できる特例措置が創設されました。
この特例は、要件を満たす土地・建物について、相続税の申告期限までに発生した災害による損失額(被災価額)を贈与時の評価額から控除し、その残額を相続税の加算対象とするものです。
なお、贈与日から災害発生日までの間、対象財産を継続して所有していなければ適用できないため、災害発生前に取得した土地・建物を手放していたときは、特例措置の対象外となります。
相続時精算課税制度を適用するメリット
相続時精算課税制度は、生前に財産をまとめて移したい場合に検討すべき制度です。
高額財産を一括贈与しても贈与税がかからない
相続時精算課税制度には、110万円の基礎控除額に加え、2,500万円の特別控除額が設けられています。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、通常の贈与は暦年課税で計算を行います。
暦年課税にも年間110万円の基礎控除額が用意されているため、贈与財産が110万円以内に収まる場合には、贈与税は課されません。
しかし、不動産など資産価値の高い財産を一括で贈与する場合には、110万円を超える可能性が高いため、贈与税の負担が生じます。
一方、相続時精算課税を選択すれば、最大2,610万円までの財産を一度に贈与しても贈与税が課されないことから、資産を効率的に一括移転したい場合に有効です。
贈与時の税負担を軽減できる
暦年課税制度では、課税対象額が大きくなるほど税率が高くなる「累進課税方式」が採用されており、最高税率は55%に達します。
たとえば、1,000万円の有価証券を贈与された場合、暦年課税(一般税率)に基づいて計算すると、231万円の贈与税が発生します。
これに対し、相続時精算課税制度を適用した場合、1,000万円の贈与を受けたとしても贈与税は課されません。
控除額を超える財産の贈与を受けたとしても、適用される税率は一律20%であるため、贈与税の負担を抑えることが可能です。
さらに、相続時精算課税制度により納付した贈与税は、特定贈与者が死亡した際の相続税の申告時に精算されます。
相続税額が贈与税額を下回る場合には、相続税の申告を行うことで、差額分の税金が還付されます。
価値が上がる財産の早期贈与で相続税対策になる
相続時精算課税制度を適用して贈与した財産は、相続税の課税対象となりますが、加算される金額は贈与時の評価額です。
たとえば、1,000万円分の上場株式を相続時精算課税制度を適用して贈与した場合、相続時点で価値が3,000万円に上昇していても、相続税の課税対象となるのは贈与時の評価額である1,000万円です。
さらに、令和6年以降は、贈与税の課税価格から年間110万円の基礎控除が差し引かれるため、贈与税の課税対象額は890万円(1,000万円-110万円)となります。
このように、値上がりが見込まれる財産を早期に贈与することで、相続税の課税対象額を抑えることができるため、相続税対策として有効です。
なお、贈与後に財産価値が下落した場合には、贈与時の高い評価額が相続税課税対象となることから、贈与のタイミングや財産の種類については慎重な判断が必要です。
収益物件の贈与で収入源を受贈者に移すことができる
賃貸物件の贈与を受けた場合、贈与後の賃貸収入は受贈者のものとなります。
毎年100万円の利益が見込める物件を名義変更せずに所有していると、その利益も贈与者の相続財産として課税対象になります。
一方で、賃貸物件を生前に贈与しておけば、賃貸収入は受贈者の所得となるため、利益分が贈与者の財産に加算されることを防ぎ、結果として相続税の課税対象額を抑えることができます。
なお、贈与を受けた後に発生する賃貸収入は、所得税および住民税の課税対象となる点には注意が必要です。
生前贈与で柔軟に資産を移転できる
相続時精算課税制度を活用することで、生前に子や孫へ資産を計画的に移転することが可能になります。
相続はいつ発生するか予測できないため、本人の意思で財産を渡したい場合には、生前贈与による資産移動が望ましい手段となります。
早期に財産を受け取ることで、資産の有効活用が可能となるほか、特定の資産を巡る相続争いを未然に防ぐ効果も期待できます。
相続時精算課税制度を適用するデメリット
相続時精算課税制度は、相続時に税金の精算を行う性質もあるため、状況次第では節税効果が得られないこともあります。
相続税の負担額が大きくなる可能性がある
相続時精算課税制度は、最大2,610万円までの贈与が非課税となりますが、110万円を超えた部分の贈与財産は、贈与者の相続発生時(死亡時)の相続財産の価額に持ち戻され、相続税の課税対象となります。
相続財産と基礎控除を差し引いた後の相続時精算課税適用財産の合計額が、相続税の基礎控除額以内に収まれば、相続税は発生しません。
しかし、合計額が基礎控除額を超えたときは相続税が発生するため、相続時の税負担が重くなる可能性があります。
一度選択すると暦年課税に戻すことができない
贈与税は、原則として暦年課税制度に基づいて課税されますが、相続時精算課税制度を適用した場合には、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことができず、相続時精算課税制度が継続適用されます。
たとえば、父からの贈与について相続時精算課税制度を適用した場合、翌年以降に父から受ける贈与はすべて、相続時精算課税制度が適用されます。
なお、課税制度の選択は贈与者ごとに判断されるため、父には相続時精算課税制度を適用し、母には暦年課税制度を適用するなど、贈与者単位で制度を使い分けることは可能です。
適用時に税務署への手続きが必須
相続時精算課税制度を適用する際は、税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」および所定の添付書類を提出する必要があります。
提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、申告時点の住所地を管轄する税務署が提出先となります。
贈与財産の価額が110万円を超える場合には、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出しなければなりません。
この手続きを怠ると、相続時精算課税制度の適用は認められず、暦年課税制度に基づいて贈与税が課税されることになるので注意してください。
贈与財産は小規模宅地等の特例の対象外
「小規模宅地等の特例」は相続税の特例制度の一つで、所定の要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額することが可能です。
相続時精算課税制度を適用して取得した土地は相続税の計算に含めることになりますが、小規模宅地等の特例を適用できるのは、相続によって取得した土地に限られます。
そのため、相続時精算課税制度を適用して取得した土地に対して小規模宅地等の特例は適用できなくなります。
相続時精算課税適用財産は物納の対象外
国税は、現金一括納付が原則となっていますが、相続税については、所定の要件を満たせば、相続財産による納付(物納)も認められています。
主な相続財産が不動産など、金銭に換価するのが難しい財産の場合、物納制度の利用も選択肢となりますが、相続時精算課税の適用を受けた財産は物納の対象とすることはできません。
相続時精算課税制度を活用する際は税理士に相談すること
相続時精算課税制度には多くのメリットがある一方で、選択後に暦年課税制度へ戻すことができない点や、相続時に贈与財産を含めた課税価格の再計算が必要となるなど、留意すべき事項も存在します。
贈与税および相続税を総合的に試算するには高度な専門知識が求められ、制度を誤解したまま適用すると、予期せぬ税負担が生じるおそれがあります。
税理士に相談することで、家族構成や資産状況に応じた最適な制度選択が可能となり、申告手続きも円滑に進めることができます。
そのため、相続時精算課税制度の活用にあたっては、早い段階で専門家への相談を検討してください。
シェアする